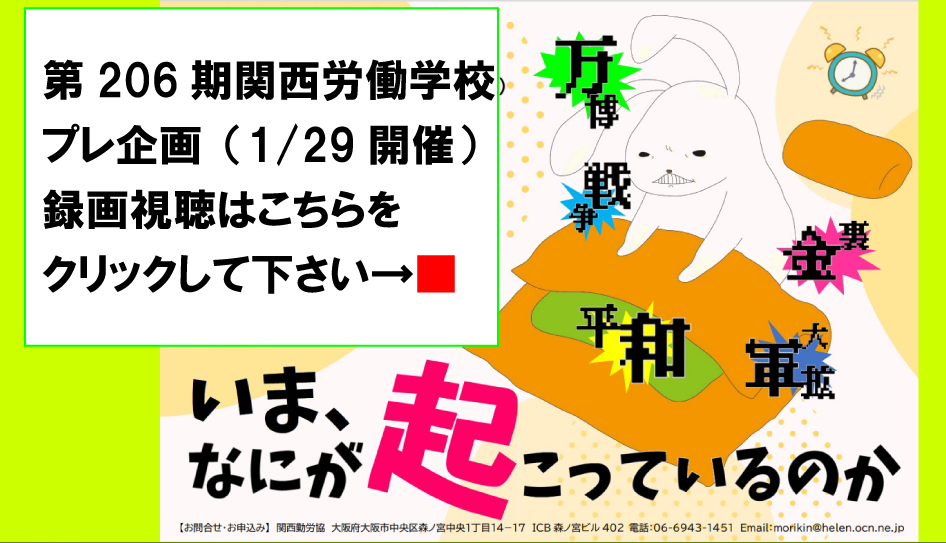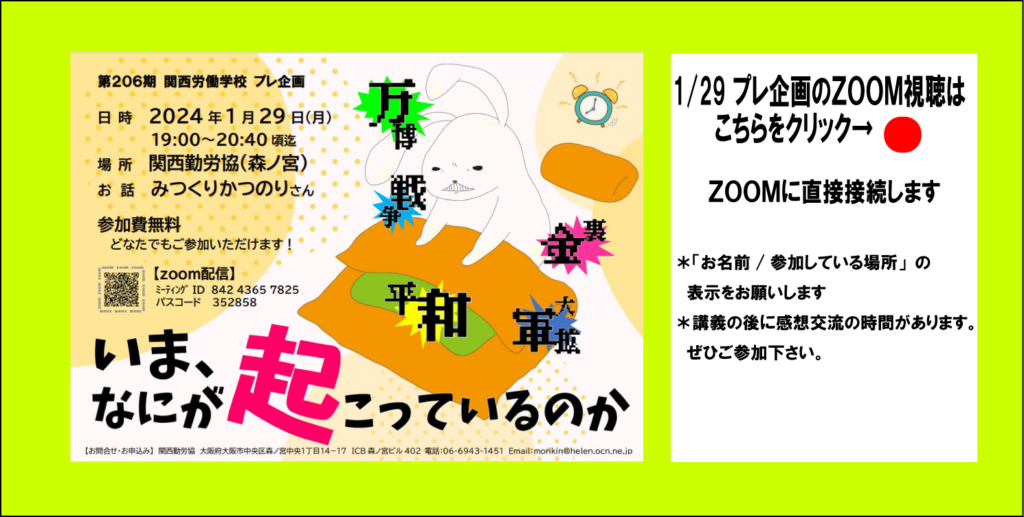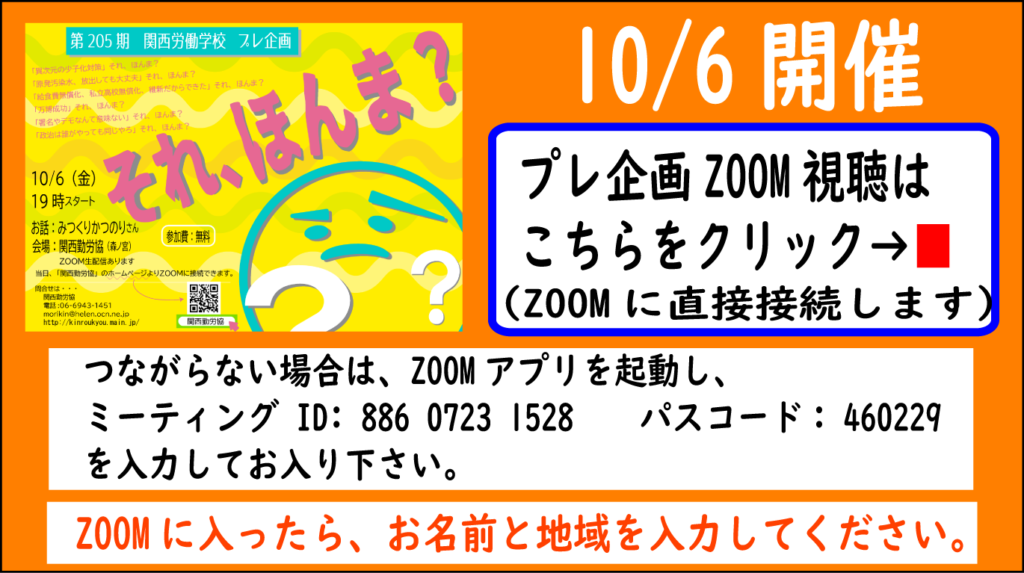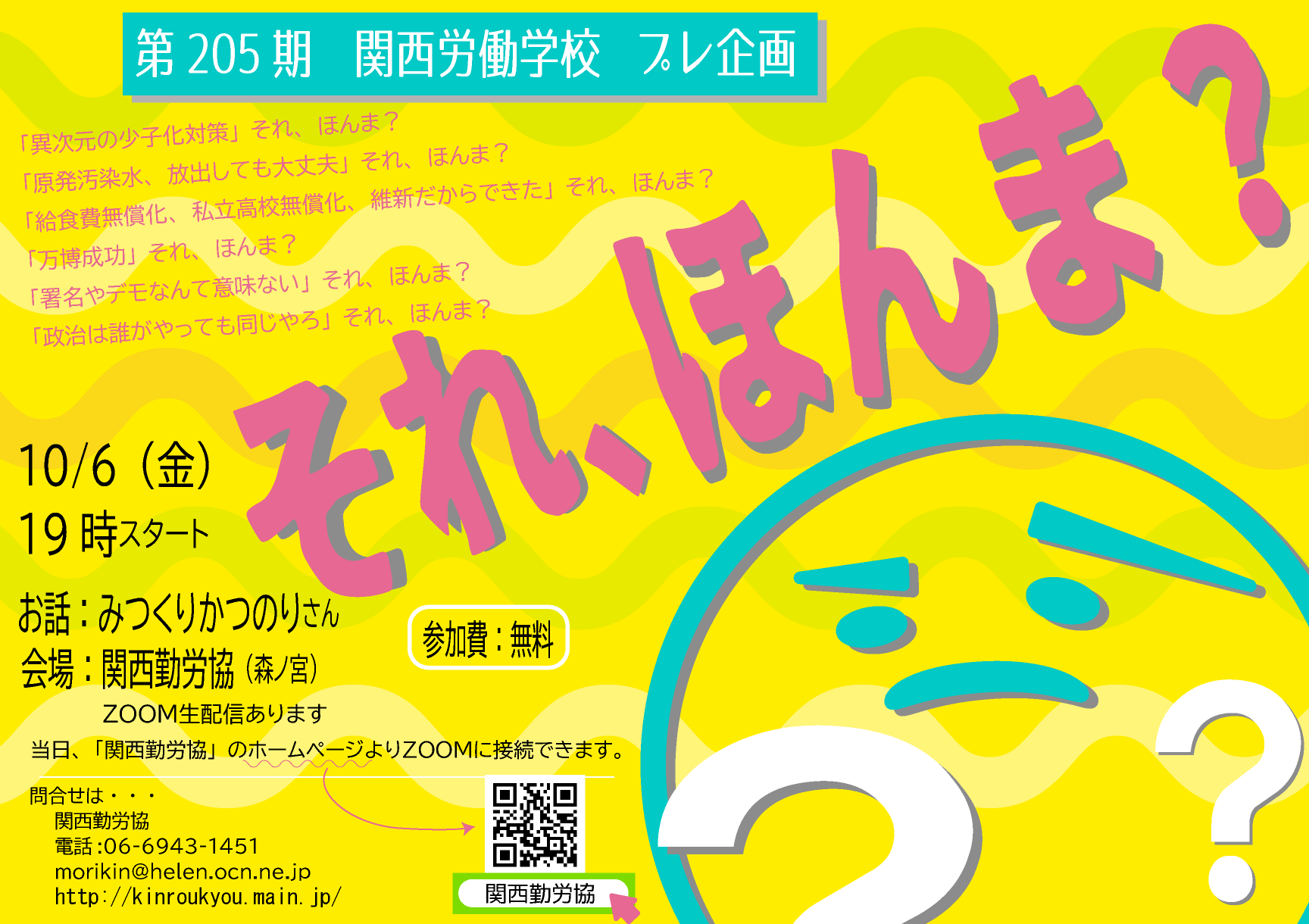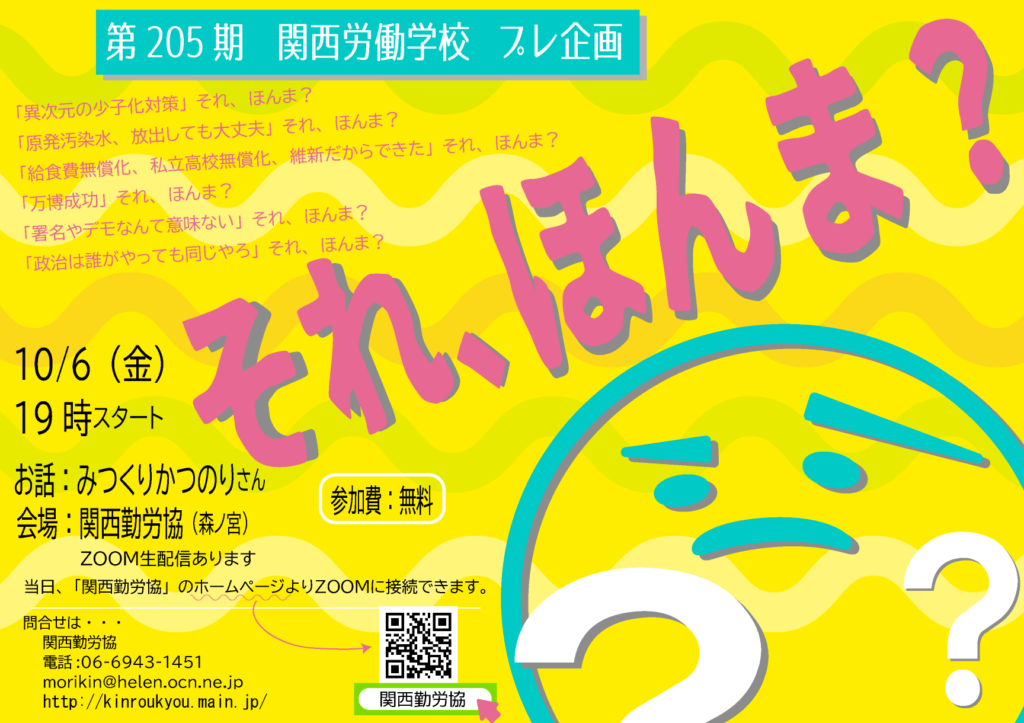【第207期関西労働学校 プレ企画のお知らせ】
忙しい、しんどい、お金がない・・・
それなのに、
「なんで学習せなあかんの?」
労働学校のプレ企画で
そんなあなたの問いに応えます。
プレ企画はどなたでも無料で参加していただける企画です。
ぜひ、お越し下さい。
:::::::::::::::::::::::::
テーマ:
なんで学習せなあかんの?
こんなに○○なのに
日時:5/31(金) 19:00
会場:関西勤労協(森ノ宮)
お話:みつくり かつのり さん
ZOOM配信あり【当日勤労協のホームページからZOOM参加できます】
参加費無料
お問合せ 関西勤労協 電話: 06-6943-1451